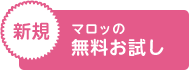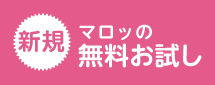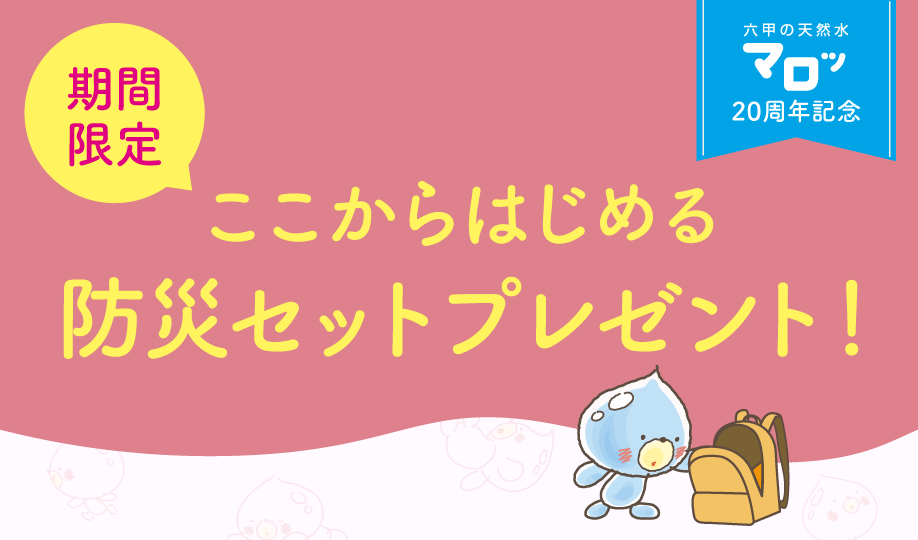七五三を祝う
イベントコラム2025年11月14日

11月15日は「七五三」。
数え年で、男の子は5歳(地方によっては3歳も)、女の子は3歳と7歳に神社・氏神に参拝し、その年まで健やかに成長したことを感謝し、これからの幸せや長寿を願う行事です。
古くは平安時代から宮中や公家で行われてきた、3歳の髪置き(かみおき)の儀、5歳の袴着(はかまぎ)の儀、7歳の帯解き(おびとき)の儀の儀式が起源とされています。
平安時代以降も武家の風習として行われ、江戸時代には商人の間でも広まり、明治時代には「七五三」と呼ばれるようになって庶民にも広まり、大正時代以降、現在のような形ができあがったようです。
七五三の食べものといえば千歳飴。
長い棒状の紅白の飴で、サイズは直径15mm以内、長さ1m以内と定められているそうです。
江戸時代、七兵衛という浅草の飴売りが、長生きするようにと縁起をかついで「千年飴」と名づけたのが始まりとか。
長寿を連想させる飴は、子どもの健やかな成長の祈願にもつながり、袋には鶴や亀、松竹梅などのおめでたい絵柄が描かれています。
七五三の料理は、子どもが主役なので、子どもの好物と、紅白を取り入れて並べ、おめでたい気分を高めるのはいかがでしょうか。
おめでたい料理の代表は、昔からお祝いの席で食べられてきた赤飯、長寿を象徴する尾頭付きの鯛、紅白のおもちなど。
子どもたちが大好きなサーモンやエビフライ、ハンバーグ、ちらし寿司やてまり寿司なども加えてください。
七五三のお祝いの席は、六甲の天然水「マロッ」をお供に。