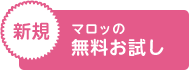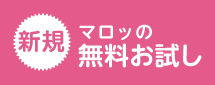米に続いて、野菜の高騰が止まりません。
しかしながら、野菜を食べないわけにはいきません。
旬の野菜をまとめ買いして、そのまま冷凍するのはいかがでしょうか。
野菜は生のまま冷凍すると味が落ちると思われがちですが、冷凍や解凍のポイントさえ押さえておけば、大丈夫。
多くの野菜は生のまま冷凍でき、面倒な下ごしらえなしで、凍ったまま調理できます。
野菜は冷凍すると繊維が壊れるため、味がしみ込みやすくなって、本来の甘みやうまみも出やすくなって、苦味が和らぎます。
冷凍野菜のメリット
- 野菜は冷蔵庫で保存すると、鮮度がどんどん失われますが、冷凍するとほとんどの野菜は3週間~1カ月ほど保存可能。とはいえ、鮮度が落ちないうちに使い切りたいもの。
- タマネギや里芋など皮のある野菜は、そのまま冷凍するので鮮度もそのまま。解凍時は凍ったまま水に1分ほど浸すと、表面の氷が溶けて、皮がツルッと簡単にむけます。
冷凍時のポイント
- 新鮮なうちに、水気と空気を遮断し、素早く凍らせて。
- 野菜はきれいに洗って水気を拭きとり、ラップで包む。
- まるごと野菜は切り口がないため、冷凍しても傷みにくく、冷凍保存袋(なければポリ袋OK)に入れるだけ。
- 保存袋に入れたら、できるだけ空気を抜く。
- 平らな状態にして冷凍庫へ。金属製バットなどがあれば、その上に乗せると時短に。
解凍時のポイント
- 解凍した野菜の再冷凍は味が落ちるので、1回で使い切るように。
- 解凍したものをそのまま食べる場合は、食べる直前に調理を。
- そのままお弁当に入れるのは、腐敗の原因になるためNG。
冷凍に向いているのは、ホウレン草や小松菜などの葉物野菜、ブロッコリーなど。
新鮮なうちに下ゆでし、小分けにして冷凍しておくと、色や食感をそのままに保存できます。
きのこ類は、冷凍によって旨味が増すという相乗効果もあります。
不向きなのは、サラダなど生野菜として食べるレタス、きゅうり、トマトなど。解凍時に水分が多く出てしまい、食感や味の変化が大きく、おいしく食べられません。
セロリやごぼう、じゃがいも、さつまいもなども繊維が多いため、冷凍によって食感や風味が大きく損なわれてしまうので、注意が必要です。
いろいろな野菜が少しずつ残ったら、「ミックス野菜」として冷凍するのがお薦めです。
キャベツや小松菜などの葉野菜は一口大に、長ネギは斜め薄切り、ニンジンは薄切りに。
1回で使う分量を冷凍しておくと、凍ったまま、野菜炒めや汁もの、鍋もの、ラーメンやパスタなど幅広く使えて便利です。
好きなときに、ムダなく使い切ることができる冷凍野菜は、食費の節約にもつながります。
六甲の天然水「マロッ」とともに、おいしく召し上がりください。
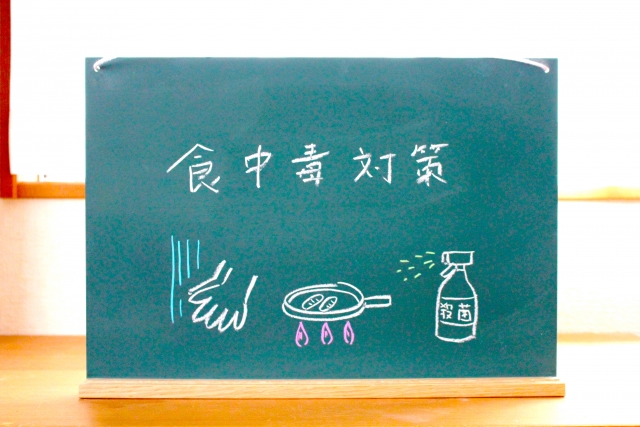
最高気温が観測史上最短期間に更新され、特に今年は酷暑が続いています。
体調管理に気をつけなければならないこの時期、食中毒の原因となる細菌にとっては増えやすい快適な環境です。
細菌による食中毒を出さないためには、食中毒予防の基本である予防3原則の徹底を。
(1)つけない=洗う!分ける!(菌を食べ物にうつさない)
(2)増やさない=低温で保存する!(菌を育てない)
(3)やっつける=加熱処理!(きちんと殺菌する)
食中毒と聞くと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭でも発生しています。普段、当たり前のことが、思わぬ食中毒を引き起こすこともあるんです。
家庭での発生は症状が軽かったり、発症する人が少人数の場合が多いため、風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず、重症化することもあります。
家庭の食事作りでの食中毒予防のポイントは6つ。
ポイント1●食品の購入
ポイント2●家庭での保存
ポイント3●下準備
ポイント4●調理
ポイント5●食事
ポイント6●残った食品
チェックポイントは数多いですが、徹底して、家庭から食中毒を追放したいもの。
食中毒はこれらをきちんと守れば予防できます。
それでも、もし、腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、お医者さんに相談してください。
参考:一般社団法人兵庫県食品衛生協会HP/厚生労働省HP
サン神戸ウォーターサプライでは、六甲の天然水マロッの水質検査を定期的に行い、お水の安全性を確かめています。
令和7年8月に行いました水質検査の結果をご報告いたします。
マロッ製品のPFAS水質検査成績表(2025年8月)
マロッ製品の水質検査成績表(2025年8月)
水質検査の結果、定められた水質基準値を下回っており、安全性が確認されています。

毎年のことですが、今年は特に、キッチンに立つのも億劫です。
暑くてコンロを使いたくない日、電子レンジ調理はいかがでしょうか。
ご飯やおかずの温め直しに使われることが一般的ですが、電子レンジにはメリットがたくさんあります。
効率よく加熱調理するため、食材100gあたり、わずか2分で出来上がります。
火を使わないので、消し忘れの心配もなく、安全です。
また、食材に含まれる水分で調理ができるので、だしや水を加えず、調味料もいつもの2/3。油分控えめでも焦げつかないため、炒め物、揚げ物も風味づけ程度の油でOK。
上手に使いこなせば、いろんな料理をおいしく、手軽に作ることができます。
おいしく仕上げるコツは
1)食材の大きさがバラバラだと、加熱にムラがでるので、大きさを均一に。
葉物野菜は下、根菜は上というように、火の通りにくい食材は、できるだけ上に乗せるのがポイントです。
2)途中で一度混ぜると、全体に火が通りやすくなります。
また、電子レンジ対応容器の下に小皿を置くと、加熱ムラ防止につながります。
3)ターンテーブル式のレンジの場合、中心から離れたほうが電磁波がよく当たることが多いので、なるべく外側にお皿を置くように。
4)レンチン後はレンジ庫内の余熱に注意を。なめらかに仕上げたい茶碗蒸しなどの卵料理は、”す“が立つのを防ぐため、すぐに取り出し、ラップも外します。
チャーシューなどは、庫内で5分ほど蒸らしておくと、芯までふっくら加熱されます。
5)皮や膜があるものは切り目を入れることで、破裂が防げます。
鶏肉は皮を突いて穴をあけ、皮を下側にして加熱。魚も表になる側の皮に斜めに1本、もしくは×の切り目を入れておく下処理を。
6)油分の少ない肉や魚は、クッキングシートを敷いておくと、仕上がりがきれいです。
7)煮物など、味をしっかりつけたいものは、食材の上にクッキングシートをかぶせ、小皿を落としぶた代わりに乗せるとよく味がしみます。
これからの季節、六甲の天然水「マロッ」と共に、レンチン調理をお試しください。

これからの季節、気がかりな災害は台風ではないでしょうか。
台風の影響で起きやすいのは停電です。
日が陰ると、暗闇の中で行動をすることになるので、ライト類の準備は必須。
明るさだけでなく、電池の種類や持続時間も確認しておくのが得策です。
LEDライトは消費電力が低く長持ちするのが特長。手回し充電やソーラー充電が可能な多機能ラジオライトは、電池がなくても充電できるため、非常時に大いに役立ちます。
一台でラジオやLEDライト、スマホの充電もできるため、最新情報を入手する手段にもなるので、確保しておきたいものです。
停電が長引くと、冷蔵庫が使えず、食料の保存が難しくなります。
レトルト食品やビスケット、アルファ化米などの長期保存食は、調理しなくても食べられるため、災害時でも安心です。
飲料水の確保は、1人1日3リットルが目安。
家族3人で2リットルペットボトル×12~18本が、飲用のみで3~4日分になるといわれています。
「六甲の天然水 マロッ」なら、5ガロン×2、または、小ボトル×3に相当します。
水と食料の備蓄は命を守る基本となるため、定期的に賞味期限をチェックし、上手に使いながら備えておくことが重要です。
停電時のライト類や情報収集に役立つスマホ充電機能付きのラジオライト、長期保存可能な食料、水などは、災害時の生活の基本をしっかり支えるアイテムです。
いざという時のために、日頃から身近に置いておき、備えを万全にしてはいかがでしょうか。